
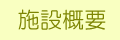
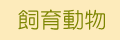
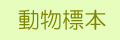
 |
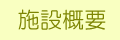 |
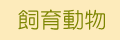 |
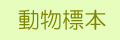 |
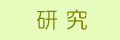 |
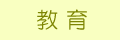 |
 |
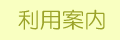 |
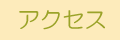 |

|
2006年6月8日 学生実習(放牧実験・後半) 前回の実習から2週間経ちました。 プロテクトケージに囲まれたところでは牧草が食べられておらず ウシたちもうらめしそうに見ていました。 ケージを外して草を刈り取り、前回の結果と合わせて 放牧されていたウシたちの採食量を算出しました。 2週間で5kg、10kg、多いと30kgも体重が増えたウシたちです。 草だけを食べてこんなにも成長する草食家畜はすごいですね。 |
 ケージ内の草は食べられていません |
 ケージをはずすと… |
 重量をはかるために刈りとります |
 前回の記録と合わせて採食量を算出 |
|
2006年6月1日〜4日 名大祭 口之島牛の牛肉販売と研究紹介 大学祭が開催されました。 さすがに設楽では模擬店も企画もなにもありませんでしたが 東山キャンパスでは当施設から出荷された口之島牛のお肉が販売されました。 リピーターの方々にちょっとした人気で、予約もだいぶ入ったそうです。 農学部の動物コース3年生たちが頑張って売り子さんになってくれました。 また、当施設で作製され、保存されている剥製や骨格などの動物標本たちが 設楽代表として東山キャンパスへ出張してきました。 農学部の研究室の紹介という企画で、これも3年生が担当してくれ 過去に先輩たちが発表した研究のポスターを貼るとともに 生きている小動物や動物標本を一緒に展示していました。 |
 大好評で売り切れ間近!! |
 いつもは設楽ですが今日は名古屋に出張して展示中 |
毎年の名大祭のなかで この農学部の研究紹介を 楽しみにしてくださる人も いらっしゃるそうで うれしいことです。 3年生のみなさん、 準備や当日のお仕事 おつかれさまでした。 |
 ヌートリア研究の発表と剥製 |
|
2006年6月1日 2校の小学校から3・4年生が集合学習に来ました 同じ郡内の小学校から社会科見学の申し入れを受けました。 珍しい晴天続きの週で職員はサイレージづくりに追われていたため 社会科見学としてお仕事の紹介などはできませんでした。 それに代わって、大学院生がいろいろな動物のお話をしました。 |
 いざフィールドへ!! 小さな研究者たち |
 院生のおにいさんと動物の調査 |
 ぼくのあげた草食べてるよ |
家畜、野生動物、移入動物… みんなで晴天のフィールドに出て、 自分の目で、自分の手で体験しました。 急なお話ではありましたが、 今まで環境教育を開いてきた大学院生が 経験を活かして対応してくれました。 小学生のみなさんの心に 何か残る 集合学習になっていたらいいですね。 |
|
2006年5月25日 学生実習(放牧実験・前半) 放牧された牛の採食量に関する実験です。 1日目は放牧前の草地の植生を調べました。 1m四方のコドラートを設置して、 中の草を全て鎌で刈りとって計量します。 対照区としては、網で囲いをつくりました。 |
 囲いの草をすべて刈りとります |
 プロテクトケージを設置 |
 みんなで牛を追い込みます |
放牧前の牛の体重も測っておきます。 まずはみんなで牛を追い込んで、 牛用の体重計まで誘導します。 方向を変えて逃げる牛に突破される場面も。 体重を測ったら、実験する放牧区へ。 2週間放牧させた後、次回の実習で 放牧後の草地と牛の体重を調べて 放牧前の結果とくらべます。 |
 放牧前の体重測定 |
|
2006年5月19〜20日 昨年につづき 工学部との合同ゼミ はじめての試みとして昨年開催した工学部と農学部の合同ゼミ。 好評を得た企画が今年も実施されました。 今年は工学部の研究室が大幅に人数が増えて 総勢40名の合同ゼミになりました。 両研究室の学生や技術職員が発表を行い 異分野間の交流を深めました。 |
 セミナー室も満杯でした |
|
2006年5月18日 学生実習(植生調査と大型機械) 今週からは、牧草地利用がテーマです。 まずは牧草地の植生調査と大型機械。 少し雨がちの空模様でしたが なんのその。 細かい草を相手に 大きな機械を相手に 学生たちはみな熱心に実習を受けました。 |
 牧草地をくまなく調べます |
 採取した草を同定して標本化 |
 操作の説明を受けます |
 実際に操作を体験 |
牧草地の植生調査では牧草地をくまなく歩き あらゆる種類の草を採取、種同定、 さいごには標本化(押し花)をしました。 大型機械は、牧草地の管理や利用に用いる さまざまな機械について、 実物を見ながら説明を受けました。 そしていくつかの機械は、学生全員が 実際に操作を体験しました。 |
|
2006年5月13〜14日 西三河自然観察会の研修会。 西三河自然観察会の自然観察指導員 のみなさんが研修会を行いました。 |
日頃交流のある自然観察指導員の方からのお話を受け、 周辺の自然環境や野生動物、また施設の飼育家畜に関して フィールドに出て話をしたり、観察をしたりしました。 大学院生の研究内容のセミナーを行いました。 院生の発表は、みなさんが日頃されている活動などにも 通じるところがあったそうで、熱心な質問や意見交換もされていました。 |
 まずは自分のイメージ・記憶だけで モグラを描いてみましょう |
→ |  標本を見てみます 標本を見てみますイメージや記憶のとおりでしたか? |
→ |  生きている状態も観察します 生きている状態も観察します動きが加わるとまた新しい発見も |
|
2006年5月11日 今年度最初の学生実習。 新しい3年生の学生実習が始まりました。 第1回目は「家畜の管理」です。 まずは実際にウシを見て、健康状態をチェックするポイントを確認。 つぎに、家畜を飼養するなかで行うさまざまな管理業務について 意義や目的を学び、さらに実際の器具や扱い方を見ていきました。 |
 |
  |
上の写真は、ウシに鼻環を装着する様子。 他には、除角・去勢・駆虫・削蹄 ウシの耳標装着について学びました。 ウシは少々大きすぎるので、 学生が実際に扱ったのはヤギです。 左の写真は、ヤギへの駆虫剤投与(左) 伸びすぎた蹄を切って整える削蹄(右) ヤギなら簡単かと思いきや・・・ 削蹄のために上手く倒して保定するのも 最初は要領を得ずに苦戦していた様子。 これも経験と慣れ、終盤は好調でした。 |
|
2006年3月24〜25日 理学部の天体観測が行われました。 1年生が学部を越えて履修できる「基礎セミナー」という授業で 理学部の先生が開講されているコースの一環です。 反射望遠鏡の凹面鏡を自分たちで磨いて そのミラーを使って望遠鏡を作るという授業です。 結局、自作の望遠鏡は制作が間に合わなかったそうですが 本格的な望遠鏡3台で天体観測をおこないました。 |
 |
 |
しばらく雨がちな日がつづいていましたが、 好天に恵まれてすてきな天体ショーとなりました。 すばる・星雲・銀河系の外の銀河・二重星・・・ なかでもみんなが一番興奮していたのは土星でした。 初めて自分の目で見る土星、はっきりと見える土星の輪に、 見た人から順番に歓声をあげていました。 右の写真は、解像度の関係でぼやけてしまっていますが、 実際は、まるで絵のようなくっきりとした土星が見えました。 |
 |
|
2006年2月25〜26日 子供たちの自然環境教育 名古屋市瑞穂区にある団体の子供たちが、 自然環境教室で当施設を訪れました。 日ごろ施設を利用して研究している学生が 環境教育の講座開講を呼びかけたところ それに応えた形で企画された講座です。 このような教育活動は、日頃は接点のない 色々な分野・立場の方々とも巡り逢えるので 私たちにとっても大変有意義な機会です。 |
 トラップがけにみんな興味深々 |
 標本を手に持ってじっくり観察 |
|
2006年2月22日 口之島牛の剥製化 当施設で系統維持されている口之島牛が 剥製として博物館に展示されることになりました。 日本在来の牛として申し出をいただいたものです。 剥製化にあたり、剥製師の方が施設を訪れ 生きた口之島牛の観察も行われました。 剥製は、上野の国立科学博物館に展示予定です。 展示が決まったら当サイトでもお知らせします。 実際に口之島牛をご覧になった剥製師さんの かっこいい牛だね、という感想が嬉しくもありました。 |
 |
|
インフォメーションです 工学部の『 モノづくり市民講座 』 当施設において、過去に農学部との合同ゼミや 技術職員の研究会をおこない交流のある 工学部の技術職員の方からご案内をいただきました。 『モノづくり市民講座 メタルクラフト2006』 平成18年3月29日(水)、30日(木) 10:00〜16:00 名古屋大学 創造工学センター(東山キャンパス)にて 1枚の銅板から工具や機械をつかって 「やじろべ」を作る講座です。 昨年開講した時の様子がこちらで見られます。 名古屋近辺にお住まいで興味のある方は 参加してみてはいかがでしょうか。 |
 |
|
2006年1月4日 あけましておめでとうございます。 今年は戌年ですね。 さて、右の写真では、軽トラックの荷台に 犬が一匹つながれています。 どんな犬なのか、わかりますか? ヒントは、写っている人の服装でしょうか。 荷台にいるということは、一緒に移動するということです。 |
 |

|
正解は「猟犬」です。 設楽には狩猟免許を持った猟師さんがいて、 猟犬として犬を飼育・調教している人もいます。 設楽フィールドで研究を進めている学生の中には、 地元の猟友会の皆さんが猟に行く時に 同行させてもらう者もいます。 研究している動物が、狩猟の対象となっている動物で 捕獲個体から研究用の試料を提供していただくためです。 また、捕獲個体の計測にもご協力いただいています。 |
 |
右の写真は、このようにして得られた ニホンカモシカの標本です。 設楽フィールドの教育や研究には 地元をはじめ各方面の方々から ご理解とご協力をいただいています。 いつもありがとうございます。 そして 今年もよろしくお願いいたします。 |
 |