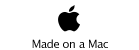新規な繁殖中枢制御剤開発による家畜繁殖技術と野生害獣個体数抑制技術の革新
詳しい情報はこちらから
女性ホルモンが脳に語りかけ排卵を引き起こす仕組みを解明
下記の新聞のほかに、NHKとCBCでニュースに取上げられたました。
中日新聞
毎日新聞
第2回世界キスペプチン会議が開催されます。
詳しい情報はこちらから
繁殖サイクルの短縮や受胎率向上のための技術開発
生殖機能を支配する脳内メカニズムの核心に迫る!
哺乳類における卵巣機能は、視床下部ー下垂体ー性腺軸によって支配されています。この一番上位にあるのが性腺刺激ホルモン放出ホルモン(GnRH)であり、1970年代にヒツジ及びブタの視床下部から発見されて以来、このペプチドホルモンの作用と、分泌メカニズムを中心に生殖内分泌学が発展してきました。
GnRHは2種類の非常に特異的な分泌パターンを示しますが、その1つが「パルス状分泌」であり、下垂体からの性腺刺激ホルモン分泌を介して、卵胞発育を司っています。もうひとつが「サージ状分泌」であり、黄体形成ホルモン(LH)のサージを引き起こして、直接排卵を誘起します。しかしながら、これら2つの分泌モードがどうやってコントロールされているかは、30年以上の間、不明でした。さらに、この2つのGnRH分泌モードは卵巣から分泌されるエストロジェンやプロジェステロンといった性ステロイドにより緻密な制御を受けています。これは正あるいは負のフィードバック機構と呼ばれ、生殖生物学の教科書では定説となっていますが、ではそのメカニズムは?というといまだ明らかにはなっていません。
この問題を解決する鍵として、われわれのみならず世界中が注目するのがキスペプチンです。キスペプチン(メタスチンとも呼ばれる)は武田薬品の大瀧らによって2001年にヒトの胎盤より発見されたペプチドで、ヒトではアミノ酸54個からなっています。ラットを用いた研究から、このペプチドが、生殖内分泌学者が永年追い求めてきた生殖の中枢ペプチドであることが明らかになりつつあり、世界中でたいへんたいへん熱い研究が進行しているのです。
本研究室では、武田薬品との共同研究を早くからスタートし、ラットをモデルとして、次々にこのペプチドの生理機能を明らかにしてきました。国内はもちろん、世界的に見ても生殖内分泌における研究をリードしていると自負しています。
世界のメタスチン研究者が集結する第1回のキスペプチン国際会議が2008年にスペインのコルドバで開催されました。この会議においても、本研究グループのメンバーは中心的な役割を演じています。また、2012年には日本で第2回のメタスチン国際会議を開催を予定しています。
最近の研究から、キスペプチンはGnRHのすぐ上流にあり、これら2つの分泌モードを制御するペプチドであることが明らかになりつつあります。また、キスペプチンは本研究室で解明しようとしてきたメカニズムを一挙に明らかにする可能性を秘めたペプチドです。外的あるいは内的な環境因子の情報はすべてキスペプチンニューロンへと入力し、GnRHニューロンの活動を直接制御しているのではないかと考えるからです。
キスペプチンにおける研究成果は、ヒトの生殖医療への応用、および畜産あるいは水産における繁殖制御技術への応用と実に幅広い可能性を持っています。それゆえに、医学及び畜産・獣医の分野でキスペプチンに熱い視線が注がれ始めているのです。